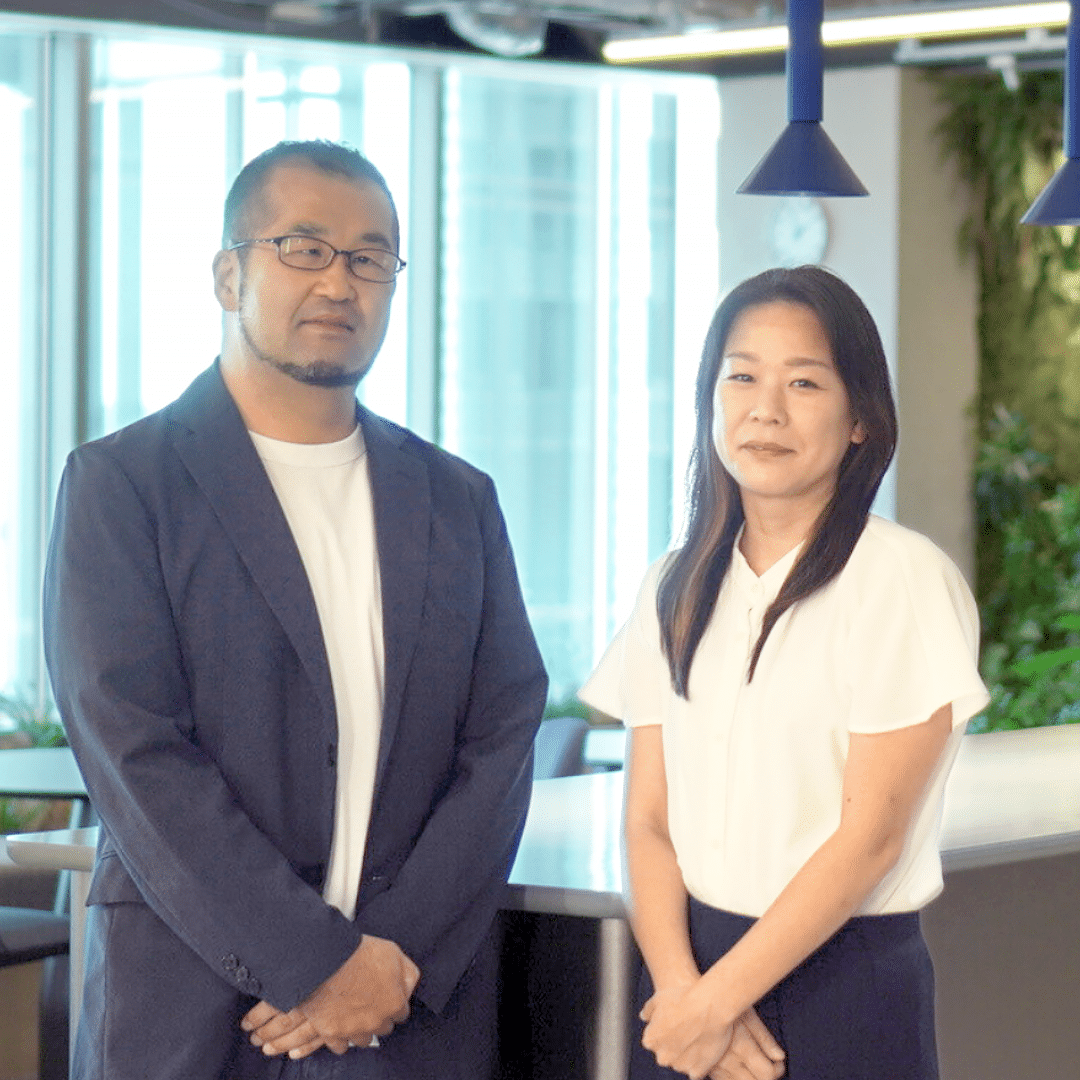導入事例 株式会社ラスコ


Smart at AIの活用で議事録件数が4倍に

株式会社ラスコ
株式会社ラスコでは、社内の議事録作成、週報のピックアップまとめ、自己評価の支援などさまざまなシーンでSmart at AI for kintone Powered by GPTを活用。効率的なデータ活用を行なっています。本事例記事では具体的な利用内容をご紹介いたします。
貴社について教えてください。
中島様:当社は1964年に創業し、半導体製造に欠かせない温湿度制御装置を中心に手掛けている会社です。精密な半導体を製造する際、一般的にはクリーンルームが使われますが、その広い環境だけでは性能が足りない場合があります。そこで当社では、より精密な温調や高いクリーン度を実現し、微細な加工を可能にする「半導体を製造するための環境を作る装置」を提供しています。
もともとは冷蔵庫や冷凍庫の製造から始まった会社ですが、物を冷やして温度を一定に保つという技術を突き詰めていった結果、精密温調の分野へと進出しました。現在では事業のほとんどが半導体関連となっており、国内外の大企業と直接取引させていただくほか、国内企業経由で海外の製造工場へ間接的に製品を納めるケースもあります。
当社の特徴は、お客様と仕様や設置環境についてゼロから話し合い、プラスマイナス100分の1度といった高精度な温調レベルまで詰めながら、その場に合わせた装置を都度設計していく点にあります。いわばニッチ寄りのカスタムメイド対応です。
また、工場設備では環境への配慮が重要視される中、各国の規制に対応しながら新しい冷媒を導入していく研究開発にも力を入れています。製品を作ることはもちろんですが、脱炭素社会の実現や持続可能な開発目標(SDGs)を推進し、環境対策にしっかりと取り組んでいる点も当社の強みです。
kintoneの導入状況について教えてください。
中島様:当社がkintoneを導入したのは2018年から2019年頃、今から7、8年ほど前になります。もともと私は電気設計の部門に所属しており、日々の業務改善のためにExcelのマクロを作成していました。少人数であれば問題なく運用できていたのですが、部署全体の約40人で使うようになると、想定外の使い方をされたり、数式が入っているセルに値を直接入力されたり、数字を入れるべき箇所に日本語が入力されたりと、エラーが頻発するようになりました。
当時は1人1つのExcelファイルを使う運用で、大元のフォーマットを各自がコピーして入力していたのですが、一元管理ができず、集計する際に、データがおかしくなっていたり、結合に失敗したりと、うまくいきませんでした。結果として「40人中5人のファイルが壊れています」といった状況が発生し、その修正も大変で、メンテナンスしきれないというのが一番大きな課題でした。Excelとマクロでの運用は限界を感じ、kintoneに切り替えたのがきっかけです。
まずは毎日の工数集計をkintoneに移行し、そこから徐々に様々な用途に活用を広げていきました。現在は工数管理に加えて、議事録や過去のトラブル事例などをまとめています。また最近では週報の運用も始めました。
Smart at AIを導入した背景を教えてください。
中島様:導入のきっかけは「使ってみたい」という気持ちが大きかったです。個人的には様々なAIサービスを使っていましたが、kintoneと連携させて業務で利用するには、難易度が高いと感じていました。特に設計部門が単独でAIサービスを探し当てて環境を構築し、データの情報流出対策やセキュリティ対策を万全にし、利用ルールを定めて導入するというのは、ハードルが高すぎました。
そのような中、Smart at AI for kintone Powered by GPT(以下、Smart at AI)であれば使い慣れているkintone上で動作し、セキュリティ対策も万全です。利用履歴もきちんと残せて、私たちにはぴったりだと感じました。
西川様: 中島が説明したように、非常に困っているところを全部突いていただいていたので、導入しやすかったです。逆に何かが欠けていたら導入できなかったと思うので、助かりました。導入から立ち上げまでの期間を短く取りたかったという事情もありました。
他のAIサービスでスタートすると、情報収集から始まって、どんなことがやりたいのかといった聞き込みだけでも、かなりの時間がかかります。その点、中島はやりたいことのストーリーを描けていたので、Smart at AIを使えばそのままダイレクトに立ち上げられました。実際、検証期間は一ヶ月ほどで、その時点である程度使えるものができていました。
中島様: kintoneで当たり前にやっていたので、あまり急に立ち上げたというイメージはなかったのですが、確かに言われてみれば、普通はそういう導入の仕方はしないかもしれませんね。
西川様: こういったシステムは導入までの時間がかかってしまうと、熱も冷めやすく、どうしてもダラダラしてしまう部分が出ます。今回は事前検証だけでいきなり立ち上げという形で進めてもらえたので、非常に使い勝手もよく、うまく活用できているというのが実情です。
Smart at AIをどんな用途で利用していますか?
議事録の作成
中島様:一番最初に導入したのは議事録の作成機能です。議事録が部署内で最も活用される機能となりました。運用の流れとしては、Microsoft Teamsで社内ミーティングを録音し、その文字起こしデータを取得します。その内容をkintoneの議事録要約アプリに登録し、Smart at AIで議事録の下書きを作成します。そして、議事録作成者が編集をし終えて完成したら、アプリアクションで議事録アプリに登録するという流れです。
文字起こしデータは精度が低いことがあり、内容の理解が難しくなることもあります。そこで、Smart at AIに「不明瞭な発言を補正してください」「文脈から意図を読み取ってください」といった指示出しています。また、人名や専門用語が正しく認識されないことがあるため、別アプリに議事録用の用語集を登録し、RAG(情報検索拡張生成)で取得する仕組みも構築しました。この用語集の活用により、精度の低い文字起こしデータからでも、意味が通る議事録要約が生成されるようになっています。
議事録要約アプリと議事録アプリを分けている理由は、議事録アプリはすでに運用しており他部署も使用していました。議事録アプリに直接AIの機能を組み込むと混乱を招く可能性があったため、前処理用のアプリを外付けする形にしました。運用が安定してからは、「gusuku Customine」を使ってAIエージェント化し、自動処理も実現しています。
西川様: 単に議事録をまとめたかったのではなく、教育にも使いたいと考えがありました。AIがある程度まとめてくれたものを社員自身がチェックできる環境を作ることで、「このようにまとめればいいんだ」ということを知ることができます。議事録を書くためのスキルアップに繋がっている面もメリットに感じています。
中島様: 議事録の作り方を部内で教育しようと試みたこともありましたが、書ける人は書けるし、書けない人は書けないという断絶が残ってしまっていました。Smart at AIである程度まで要約してくれれば、最後の少しを修正するだけで議事録が完成するので、その部分は大幅に改善されました。
導入後の効果は顕著で、2025年7月の導入以降、議事録が作成される件数が3〜4倍に増加しました。今まで記録を残していなかった社員も、気軽に議事録をまとめてくれるようになっています。せっかく会議をしているのに記録を残さないともったいないですし、別にみんな残したくなくて残していないわけではないと思います。楽に残せるようになれば、自然と記録が蓄積されていきます。
週報のピックアップまとめ
中島様: 2つめは週報ピックアップです。もともと週報は全員が毎週書いていました。各メンバーが毎週木曜日にまとめ、その後チームリーダー、上長へとエスカレーションしていく流れです。週報は書いているものの、活かしきれていないという課題がありました。今、週報を書いているのが27人ほどいますが、全員分をすべて目を通すのは現実的に難しく、特に見直しのきっかけがありませんでした。
そこで、週末までに書かれた週報を、週明けにRAG機能で拾ってきて自動的にまとめる仕組みを作りました。弊社では「バッドニュースファースト」という方針で、悪いニュースから先に書くルールになっています。共有する必要があるバッドニュースをまず表示していました。ただ若手から「バッドニュースばかりで気が滅入る」という意見があったため、グッドニュースも表示するようにしました。その他に、複数人が言及していることや特徴的な内容も抽出しています。
まとめが完成すると、kintoneのリマインド機能を活用してレコード作成時に部署内へ通知を送信し、「今週のまとめが出来上がりました」という形で情報を共有しています。このまとめ作業により、「同じことを気にしている人もいるんだな」や「こういうプロジェクトも進行しているんだ」といった気づきが生まれ、部署内の情報共有が大幅に改善されました。
西川様: 特にマネージャーにとっては非常に見やすくなりました。今まで全員の週報を見ていましたが、追いつかなくなってしまい、中島に相談したところ、このまとめ機能を作ってくれました。
中島様: 週報アプリの開発は、相談を受けてから実装完了まで数日程度という短期間で行われました。仕組みとしては、適切なプロンプトを作成し、週の始めに自動的に内容が生成されるようエージェント化しています。また、元のレコードへのリンクも自動生成される機能を実装したため、興味を持った内容があればすぐに詳細確認ができる利便性も備えています。
週報を活用した自己評価の支援
中島様: 当社では半期ごとに評価があり、自己評価を提出する必要があります。しかし、「半期が終わったので評価を出してください」と言われても、直近1〜2ヶ月のことしか覚えておらず、4月頃にどんな仕事をしていたかは思い出せないという問題がありました。
そこで、せっかく毎週書いている週報を活用することにしました。半年分の週報をRAGで拾ってきて、社内の評価項目に紐づいた分析観点を設定し、得点、充足している点、不足している点、次の取り組みとして何をすべきかをAIに分析させています。
これは自分が書いた内容が半年分まとまっているので、納得感が非常に強いです。AIが勝手に何かを持ってきたわけではなく、自分で書いたものがベースになっているため、納得いかないわけがありません。また、充足している点や不足している点、次の目標をどうすべきかといった提案型のフィードバックが得られるため、「ああ、そういうところをやらなきゃいけないんだな」という気づきにもなります。
さらに、直接人から言われているわけではないので、少し厳しいことを言われても「まあ、AIが言うことだし」と受け入れやすいという心理的な効果もあります。これは評価される側だけでなく、評価する側の負担軽減にもつながっています。現在は定期業務化はしていませんが、月末に回数制限の余裕がありそうな時に試験的に展開しており、評判は非常に良好です。
CADに関する問い合わせ対応
中島様:現在、3D CADの入れ替え業務を進めており、毎週の定例会議で決定事項を議事録にまとめています。この議事録をRAGとして設定し、Q&Aアプリに質問を入力すると、「こういう流れで、今はこう決まっています」という内容を議事録から抽出・整理してくれる仕組みです。
ユーザー向けというよりも、現在は私自身が全体の進捗を把握するために活用しています。「この内容、結局どうなったんだっけ」「この機能の最終決定は何だったか」といった確認が必要なときに、該当の議事録部分を抽出し、「この日はこう話していて、現在はこう決まっています」といった情報の流れをまとめてくれるので、ガイドラインなどの資料に落とし込む作業にも役立っています。また、日付の新しいレコードを最終版として優先度を高く設定し、確定情報だけをまとめたダミーレコードも作成しています。
AIで内容を確認し、「こう決まった」と判明したものは、その確定情報レコードに追記し、最終決定として整理しています。以前は、キーワード検索で議事録を探し、該当箇所を見つけて手動でまとめ直す必要がありました。しかし、この仕組みでは関連情報を自動で抽出してくれるため、元のレコードにもすぐにアクセスできます。毎週の議事録を1つの書類にまとめる作業は手間がかかり、情報がまとまらないと周囲にも不安を与えてしまいますが、このQ&A機能により、その課題をうまく解消できたと感じています。
効果はいかがでしたか?
中島様:具体的な数字で言うと、議事録の作成件数が大幅に増えたのが最も顕著な効果です。現在は毎月約20件の議事録が生成されており、これはほとんど新たに生まれたものです。以前は数件程度しか登録されていなかったため、明らかな増加が見られます。
西川様:議事録の書き方がわからないという社員も多くいました。Smart at AIの導入と、中島が構築してくれた運用体制のおかげで、誰でも気軽に議事録を作成できるようになりました。新たに作成し始めたメンバーのうち、約3分の1は若手社員で、新入社員も含まれています。そのメンバーが積極的に議事録を作成できるようになったのは、大きな効果だと感じています。
中島様:導入により、議事録の作成時間も大きく短縮されました。苦手な人はゼロから作るのに時間がかかり、録音データを何度も聞き直して作成していました。工数削減というよりは、それまで議事録が作成されていなかったことで失っていた情報を、しっかりと記録として残せるようになったことが大きな成果です。
Smart at AIに対して要望はありますか?
中島様:事例を多く知りたいと考えています。自社に適用できるものがないか探りながら、活用の可能性を広げていきたいと思っています。参考にしている情報としては、ペパコミさんの事例がとてもわかりやすく、取り組み内容が的確に説明されているので、YouTubeなどを見ながら「これは自社でも使えそうだな」と考えることがよくあります。
また、M-SOLUTIONSさんのセミナーを参考にして作成したのが、先ほどの週報まとめアプリです。具体的な事例が紹介されていて、とても助かっています。情報収集は主に動画から行っており、テキストだと細かなニュアンスが伝わりにくいことが多いため、AI関連の内容も動画の方が「なるほど、こういうことか」と理解しやすいと感じています。
今後の展望がありましたら教えてください。
西川様:私の最終的な目標は、Smart at AIを活用して設計ができるようにすることです。現在はその準備段階として、必要なデータをkintoneに入力しており、「設計案はkintoneとSmart at AIで作成できる」と言える状態を目指しています。設計に必要な専門用語や仕様データ、計算式をkintoneに蓄積し、議事録も残していくことで、用語などの情報は着実に増えてきています。今後は、設計案も自動で出力できるようになると考えています。
さらに活用が進めば、営業にもkintoneとSmart at AIを展開したいと考えています。お客様へのヒアリングの段階で活用できれば、非常に効果があると思います。例えば、お客様の要望に対して「似たような事例はこれです。加えてこの情報があれば、さらに絞り込めます」といったアドバイスができれば、やり取りもスムーズになり、製品納入までのスピードも向上し、他社との差別化にもつながります。
営業が詳細な情報を事前に取得できれば、設計部門の負担も軽減されます。最初に得られる情報が具体的であればあるほど、設計側の手間も省けます。こうした使い方を今後さらに発展させていきたいと考えています。
最後にSmart at AIを検討している方にメッセージをお願いいたします。
中島様:最新のAI動向を自社だけで追うのは難しいため、その部分はプロダクトに任せ、自分たちは本当に取り組みたいことに集中できるのがSmart at AIの大きな利点です。非常におすすめです。セキュリティ面でも安心でき、kintoneの基本機能と連携できるため、Smart at AIで作成した内容を通知したり、プロセスの進行に応じて動かしたりすることも可能です。kintoneとSmart at AIの役割をうまく分けて共存できる点も魅力です。
スピーディーな立ち上げにも対応でき、kintoneのアプリ作成やSmart at AIのプロンプト作成も迅速に進められます。kintoneでデータや情報が蓄積されてきた方にこそ、ぜひ使っていただきたいです。長く使うほど、より効果的に活用できると思うからです。
株式会社ラスコについてはこちら
資料ダウンロードはこちら 無料トライアルはこちら お問い合わせはこちら![Smart at M-SOLUTIONS[stg]](https://smartat.jp/wp-content/uploads/2023/02/logo.png)